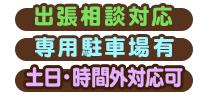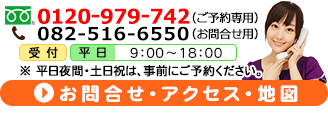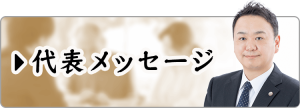遺留分侵害額請求への生前対策 【第1回】
1 はじめに


今回は「遺留分侵害額請求」に対し、生前に何らかの対策ができないかについて、第1回目の説明をさせていただきます。
遺留分制度は、相続財産のうち、その一定割合を一定の相続人に保障する制度であり、法が一定の相続人に対して最低限の分配を保障しているものです。
しかしながら、ご自身が生前に残した財産を、「この相続人には絶対渡したくない、渡すにしてもできるだけ少なくしたい」などのご希望を持たれる方も一定数いらっしゃいます。たとえば、不良的な行為をしてきた子、財産を散逸する子などに財産を渡したくないというのも理解ができるところです。
そのため、そうしたご希望に添った対策も必要となってきます。
2 対策1:「遺留分の放棄」について
以前、別の記事「遺留分制度の概略について①」においてもふれましたが、自身の生前(相続開始前)に法定相続人に話をし、その法定相続人に家庭裁判所の許可を得て遺留分放棄をしてもらうことが考えられます(民法1049条1項)。
たとえば、生前に一定の援助をするのと引き換えに「遺留分の放棄」を行なってもらうということも考えられます。
ただし、「遺留分の放棄」は、申立人の自由な意思に基づくものでなければ、家庭裁判所も遺留分の放棄の申立てを却下します。
たとえば、被相続人が遺留分権利者対象の相続人に対し、強い干渉によって無理矢理に遺留分の放棄をさせようとしたり、「将来、お金を渡すから遺留分を放棄しておきなさい」と促し、そのお金が渡される真偽が不明な場合などのケースでは、「遺留分の放棄」の申立てを却下されてます。
3 対策2:「遺言書の作成」について
⑴ 遺留分対策において、「遺言書」の作成は、最優先事項となります。
まずは大前提として、ご自身が財産を託したい相続人等に対して、「相続させる」、「遺贈する」ことを遺言書に定めておかなければいけません。
そして、最近よく目にするのが、遺言書の中で「付言事項」を定めておくことで遺留分対策をしようとすることです。
「遺言書を通して、お世話になった人への感 謝、家族や自分が大切にしてきたものへの気持ちや願いなどを伝えることが一般的に行われていますが、この感謝や気持ち、願いを伝える文章を「付言事項」といいます。」(文例の記載もあるので、「仙台法務局HP」をご紹介します。)
「付言事項」という自身の気持ちを示しておく項目内で、「なぜこういう配分の遺言を残したか(よく面倒をみてくれたとか)」、「生前、生前贈与をいくら渡したから、遺留分侵害額請求を行使して欲しくない」ということを記載しておくわけです。
専門職が関与する事案では、専門職が遺言執行者となり、遺言を相続人に明らかにし、「相続人間で争わないでくれ」等の生前の被相続人によるメッセージビデオ録画をみせ、遺留分侵害額請求を行使しようとする人に対して心情的に訴えかけ、遺留分侵害額請求を行使させないために「遺言者の生前の意思を無駄にするのですか」と説得するケースもあるようです。
しかしながら、こうしたメッセージ的な付言事項は法的には意味がありませんし、遺言執行者に遺留分侵害額請求の行使を妨げる権限もありません。
また、裁判の中で、『「付言事項」に書いてあるから贈与があるはずだ』だけでは、立証不十分であるといえます。
遺産を独り占めしようとする他の相続人関与のもとに遺言書の作成をさせるケースなどで「付言事項」を悪用することも考えられます。
「付言事項」による遺留分侵害額請求への対応としては、特別受益や寄与分の証拠の一つとして、具体的な贈与の記載(金額、贈与の日付、その贈与がそういった経緯でなされたかなど)、寄与の具体的な内容(どういったサポートを受けてきたか、その財産にあたえる影響など)を記載しておくことが考えられます。ただし、重複しますが、その記載のみでは特別受益や寄与分の認定には不十分ともいえますので、生前における金銭振り込みの証拠として通帳や振込票などの客観的な証拠も揃えておくことが重要であるといえます。
⑵ 「遺言書」で一定の財産をあえて遺留分侵害額を請求しそうな相続人に振り分けるということもありえます。
たとえば、金額ベースで遺留分に近い金額を渡すことを遺言書に記載しておくなどです。
被相続人と財産を取得させる相続人等の当事者間ではあまり重要ではないですが、財産的価値は一定程度見込まれる不動産・動産の相続をさせることを記載しておくことなども対策として考えられます。
⑶ なお、遺言書に、「遺留分侵害額の請求の順序」も記載しておくことも考えられます(民法1047条)。
財産を相続させる人が複数人いる場合には、請求の順序の記載について一定の考慮をしたほうがよいといえます。
4 さいごに
相続人に対して、遺留分ですら渡したくないという要望があり、生前から遺留分対策をしておきたいということにご関心がおありの方は、相続に詳しい弁護士に相談されることをお勧めします。