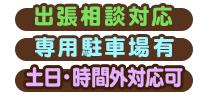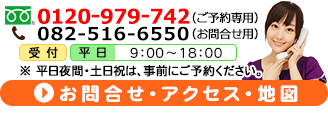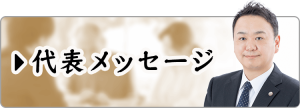遺言の基本的な書き方(遺贈について)
1 はじめに
「遺言」についての具体的な書き方について、気になる点をシリーズでご紹介をしていきたいと思います。
まずは、「遺贈」(民法960条)についてご紹介をさせていただきます。
「遺贈」には、『包括遺贈』と『特定遺贈』があります。
『包括遺贈』は、遺贈が包括名義でなされる場合です。
『包括遺贈』には、全ての財産を特定の方に渡す「全部包括遺贈」と、遺産のうち何分の一かをどなたかに渡す形式の「一部包括遺贈」があります。
例えば、「全遺産は甲に遺贈する(あげる)」というものが全部包括遺贈です。一方,「遺産の3分の1についてはAに遺贈する(あげる)」というものが一部包括遺贈です。
遺言者の全財産を割合的に遺贈しているので『包括遺贈』と呼ばれます。
これに対し、『特定遺贈』は個々の財産を特定した上で遺贈をしています。
例えば、「甲土地をAさんに遺贈する」などの形式になります。
2 『包括遺贈』について
『包括遺贈』については、「包括受遺者は、相続人と同一の権利義務を有する。」(民法990条)と定められています。
『包括遺贈』を受けた方については、相続人と同一の権利義務を有するので、借金などの負債も、効果遺贈を受けた割合に応じて、負うことになります。
被相続人(遺言者)が連帯保証債務を負っている場合も、包括遺贈を受けた方もその債務の責任を負ってしまいます。
さらに、『包括遺贈』を受けた方については、財産を割合的に受けとるため、他の法定相続人の方と同列で遺産分割手続きをすることも考えられます。
また、『包括遺贈』を放棄するのも相続放棄と同様に、3ヶ月以内に行なわなければなりません。
3 『特定遺贈』について
『特定遺贈』については、法定相続人でない方は、『包括遺贈』と異なり、被相続人(遺言者)の負っている債務を負担しません。
そのため、たとえばお世話になった方、お世話になった施設などに感謝の意味も込めて、ご自身の遺産を渡した場合には、『特定遺贈』として、特定の財産を渡す遺言とすべきです。
『特定遺贈』であれば、相続人の方と同一の権利義務を有しませんので、遺贈の放棄をする場合にも、3ヶ月以内に行なわなければならないという制限もありません(民法986条 「受遺者は、遺言者の死亡後、いつでも、遺贈の放棄をすることができる。」)。
では、法定相続人の方に対して、『特定遺贈』をした場合、どうなるのでしょうか。
被相続人(遺言を残された方)に資産と負債がある場合を考えてみましょう。
『特定遺贈』を受けた法定相続人の方は、その遺贈された財産だけを受け取った上で、相続放棄をすることも可能です。相続放棄をすることで負債を負わなくてもすみます。
ただし、こうした特定遺贈に対して、遺留分侵害額請求をされるおそれがあること、債権者から詐害行為をして特定遺贈の取り消しを求められる可能性もあるので注意が必要となります。
そのため、こうした『特定遺贈』を駆使して遺言を作成する場合、弁護士等の専門家のスクリーニングを経て、作成するのがよいと思います。
4 さいごに
「遺言」の作成につきましては、遺言の内容の精査など事前の準備が必要となることも多いです。
「相続させる」旨の遺言、『包括遺贈』、『特定遺贈』などどういった形で財産を渡すか、遺言の文言で法的な効果も変わってきます。
そのため、遺言の内容をどうするか、という点においても相続に詳しい弁護士にご相談をされることをオススメします。